この記事では、プロジェクトマネージャ試験の午後Ⅱ論文のパーツ(プロジェクト計画・統合マネジメント領域)をサンプル論文とともに公開します。
サンプル論文を掲載する理由は、「プロジェクト計画・統合マネジメント領域における論文のパーツ」を提供するためです。なぜパーツを提供するのかというと、午後Ⅱ試験の具体的な対策として、論文をパーツを準備しておくことが有効な方法だからです。
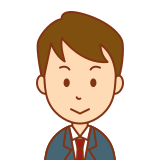
アママネくん
プロジェクトマネージャの実務経験もないのに、プロジェクトマネージャとしてプロジェクト計画・統合マネジメント管理した経験を2000字も論文にするなんて難しすぎる・・・
プロジェクトマネージャ試験の午後Ⅱで、問題文を見てゼロから2000字超えの論文を書き上げることなんて不可能だと思いますよね。しかも、問題文に合わせる必要があるので、予め作っておいた論文を書いてもテーマに沿わない可能性が高く、それでは合格の確率は極低いです。
アママネくんのこの感覚は正しいです。プロジェクトマネージャ試験のプロでないかぎり、「準備無し」で合格論文を書くのは無理です。
ではどうすると良いかというと、準備をしておくんです。具体的に準備というのは、使い回しできる論文のパーツを用意しておくことです。
パーツの準備が有効である理由は、別の記事で深掘りしてまとめます。
私は都内の上場IT企業で、プロジェクトマネージャ試験対策の社内勉強会を2016年から主催しています。その活動の中で午後Ⅱ論文の添削をやっています。年40本として、合計で250本は添削しました。
ここでは、私が添削した午後Ⅱ論文の中から、「合格レベル」と言い切れる水準の論文をいくつかピックアップしてみます。ぜひ、午後Ⅱ論文のパーツとして使用してみてください。つまり、つかえそうなところがあったら、パクってみてください!
- プロジェクトマネージャの実務経験なしだけど、プロジェクトマネージャー試験を受験する人
- プロジェクトマネージャ試験の午後Ⅱの論文のネタ、もしくは論文パーツ等を探している人
- プロジェクトマネージャ試験の午後Ⅱにおいて、プロジェクト計画・統合マネジメント領域を勉強している人
プロジェクトマネージャ試験 平成14年 問2 業務仕様の変更を考慮したプロジェクトの運営方法について
平成14年 問2 問題文
近年,インターネットを用いた新しいビジネスモデルの構築など,未経験領域のアプリケーションが増加している。アプリケーションによっては,プロジェクトの初期の段階で業務仕様をすべて定義しきれなかったり,早期に凍結できなかったりすることがある。
このような場合,プロジェクトの立上げに際しては,まず,全体の業務仕様のうち,変更の可能性のある部分とそれらの変更の発生時期を,利用者の協力を得て可能な限り予測することが肝要である。そして,業務仕様の変更に柔軟に対応できるようプロジェクトの運営方法に工夫を凝らす必要がある。そのために,例えば,次のような事項を検討する。
・プロジェクトの初期の段階から利用者がプロジェクトへ参画する。
・短いサイクルで段階的に開発するなど,変更に強い開発プロセスモデルを採用する。
・予想される変更の影響を局所化できるように設計を工夫する。
・開発期間,費用に余裕を含めたり,見直し時期や調整方法を顧客と取り決めたりしておく。
プロジェクトの実行に際しては,個々の変更要求に対して,様々な観点から評価する。例えば,利用部門から見た変更の緊急性や効果,変更しないことによる不便さの度合い,開発部門から見た開発期間や費用への影響などを総合的に判断して,採用の可否を決める。また,必要に応じてプロジェクト体制やスケジュールなどを調整する。
あなたの経験と考えに基づいて,設問ア~ウに従って論述せよ。
平成14年 問2 設問文
設問ア あなたが携わったプロジェクトの概要と,プロジェクトの立上げの際に変更の可能性があると予測した業務仕様とその理由を,800 字以内で述べよ。
設問イ プロジェクトの立上げに際して,業務仕様の変更に柔軟に対応するためにどのような事項を検討したか。また,プロジェクトの実行に際して,業務仕様の変更に対してどのように対応したか。工夫した点を中心に述べよ。
設問ウ 設問イで述べた活動をどのように評価しているか。また,今後どのような改善を考えているか。それぞれ簡潔に述べよ。
平成14年 問2 サンプル論文
1-1 プロジェクトの概要・特徴(269字)
私はシステム開発ベンダーZ社のプロジェクトマネージャーである。今回私が担当したプロジェクトは、東京都で外食チェーン店A社の、店舗販売状況をリアルタイムで可視化するBIシステムの導入である。機能としては、可視化・分析・未来予測、といったものだ。特徴としては、ユーザーがBIシステムの導入は未経験だったことと、コロナ禍の影響で外食産業の業績が悪化してコストの制限が非常に厳しく、予備費がわずか3%程度しか用意されなかったことだ。体制は2チーム最大8人・総工数約60人月・PJ期間は2020年4月~2021年2月の10ヶ月であった。プロジェクトの目的としては、BI導入より、販売方法やマーケティング方法を柔軟に変更できる社内の構造を作ることである。
1ー2 変更の可能性があると予測した業務仕様とその理由(348字)
2020年3月時点の計画策定中に、変更の可能性があると予測した業務仕様は、店舗売上の業績分析用ダッシュボード画面の活用方法である。この理由は、コロナ禍があったからだ。2020年3月中旬から東京都ではコロナ禍による緊急事態宣言が出され、外食産業は大きく外部環境が変わっているところだった。例えば、既存店舗の運営がどの程度制限されるのか、7月から開始予定となっていた宅配モデルが成功するのか、といった状況は全く見えていなかった。
しかし、コロナ禍だからこそ、早期判断のために、店舗の売上状況をリアルタイムで知る必要がある、という判断をA社社長はした。画面仕様が固まらないというリスクはあったが、リスクを的確にコントロールすれば、A社ビジネスモデルの変革に繋がる情報が手に入る、と考え、メリットの方が大きいと考えた。
2ー1 業務仕様の変更に柔軟に対応するために検討した事項(786字)
まず、全体の業務のうち、変更の可能性のある部分と、それらの変更の発生時期を、利用者の協力を得て予測した。この理由は、スコープを監視するして要件変更の膨張を防ぐことが、厳しいコスト目標を遵守するために必須と考えたからだ。具体的には、スコープを監視する際の重点項目を洗い出すために、BIシステムにおけるどの業務(およびどの画面)が変更になりそうか、を洗い出した。ヒアリングを重視し、社長および店舗販売を統括する販売部門長の協力を得て、今後のA社の事業方針と実施施策をヒアリングした。
結果、対象の業務(および画面)は店舗の宅配売上の可視化に関連する部分であると判明した。コロナ禍だとしても店舗売上を構成する要素(客回転率やリピーター率など)は変わらず、要件は見通せる。一方で、宅配売上は計画立案時の3月時点で企画段階だったために、重要な指標が定まっていなかった。
宅配売上の可視化をするサブシステムに変更が発生するリスクを定量分析すると、外部設計の6月7月に発生する確率は80%を超えるほど高く、影響も非常に大きかった。ここで、宅配業務の開始は7月である。そのため、6月以前に検討した要件および外部設計内容が、7月になって変更となる可能性は大きかった。逆に、8月になれば宅配はサービス開始後1ヶ月を迎え、A社として重要な指標も推測できるような状態になり、変更が発生するリスクは小さかった。
そこで、3月末の全体計画策定の末期に、変更に強い開発プロセスモデルとして、外部設計においてプロトタイプモデルを採用することを各チームリーダーに指示した。プロトタイプモデル採用の理由は、6月7月の外部設計中に画面のプロトタイプを見せることで、ユーザーに具体的な活用手法と画面項目をイメージさせることである。結果、外部設計の品質を早期に高め、先の工程で手戻りを生じにくくさせることが目的である。
2-2 業務仕様の変更への対応(928字)
プロトタイプの採用により、7月以降に発生すると考えられる宅配状況BIシステムの画面に対する変更は、少なく抑えられた。Z社における同規模の標準的なBIプロトタイプと比較すると、外部設計以降の変更要求は、70%少なかった。
しかし、それでも7月以降に業務仕様への変更は発生した。例えば、宅配販売の販売状況は、想定以上に米Uber社等の流通業者のキャンペーン状況に左右される、などといったことが判明した。そのため、業務仕様としては、宅配売上の未来予測値を出力値とする場合、予測の精度を高めるため、流通業者のキャンペーン状況を入力値としたい、といったような変更だ。外部設計後半の7月~内部設計完了の9月までで、大小の規模はあるが、15件ほどの変更要求が生じた。
そこで、ここでは、個々の変更要求に対する、様々な評価を行い、変更を受け入れるかどうかを変更管理委員会にて判断した。判断の重要な要素は以下である。
・利用部門から見た変更の緊急性や効果
特に効果を重視した。ここでの定義の効果は、その変更を適用させると、「BIシステムとしての機能強化に繋がり、最終的に売上状況の判断や今後の意思決定へ繋がる情報を早期に出せるようになるか」であるとした。定義を明確にしておくことで、評価のばらつかないようにするためだ。最終的には、利用部門にとって重要な変更かどうかを、1~5段階の評価で数値化した。
・変更しないことによる不便さの度合い
これは効果と裏返しの関係となる。効果と同様に数値化して評価した。
・開発期間や費用への影響
変更することで開発期間や費用への影響が大きいほど、評点を低くした。本件は特に費用の制約が大きいため、費用への悪影響が大きい変更は、重み付けを強くして、評価が低くなるように設定した。。
・採用に伴う、プロジェクト体制やスケジュールなどの調整
本プロジェクトの場合は、最終的には40%(6件/15件)の変更を受け入れた。全てA社に起因する変更であることから、変更受け入れることによる工数の増加分は、A社が負担することになり、ここでは3%の予備費を全て使うこととなった。具体的には、変更による遅れを取り戻すためにクラッシングを用い、体制を強化することで乗り越えたのである。
3-1 私の評価(473字)
評価としては、非常に高いものと考えている。理由としては、①プロジェクトの目的であった販売やプロモーションの柔軟な運用に繋げられたこと②プロジェクト目標として強く掲げられていたコスト目標をクリアできたこと、が挙げられる。具体的には、①ではBIシステムリリース後の2021年5月に、宅配販売の大幅強化(流通業者の追加やQRコード決済等のキャッシュレス決済の追加)に繋げられたことが挙げられ、A社販売部門長や社長からも大きな感謝を頂戴できた。②では、コンティンジェンシー予備費は使ったものの、辛うじて予算内に収まった。
この理由としては、計画時に定めた(a)プロトタイプの採用と(b)基本的な変更管理方法を徹底したことが奏功したと考えている。前述の通り、プロトタイプの採用により、Z社における同規模の標準的なBIプロトタイプと比較すると、外部設計以降の変更要求は、70%少なかった。さらに(b)変更管理方法の徹底では、15あった変更要求を4つにまで絞り込むことができた。また、これは、スコープ変更の膨張を防ぐために、スコープの量を監視していたことも大きかった。
3-2 今後の改善点(352字)
今後の改善点は、プロトタイプ技法の標準化である。本プロジェクトの成功に貢献したBIにおけるプロトタイプモデルの採用は、今後も有用であると判断できる。一方で、Z社にはプロトタイプモデルの採用経験者が少なく、要件定義~外部設計時のプロトタイプ作成には、一部、予定以上の残業でカバーしたところがあった。具体的には、6月~8月は、計画以上の残業がメンバー1人あたり平均で毎日1時間程度発生しており、ここでコンティンジェンシー予備費を使っていたのである。
本プロジェクトで培ったプロトタイプモデルの知見は、「顧客に見せるプロトタイプの完成度合い」「プロトタイプに必要な画面項目の例」「プロトタイプが挙動する際の適切なレスポンスタイム」などが挙げられる。これらを可能な限り定量化し、今後のプロジェクトで活用したい。
まとめ
午後Ⅱの解き方そのものは、プロジェクトマネージャ試験対策として最強の参考書であるはみよちゃん本こと、翔泳社の「情報処理教科書 プロジェクトマネージャ」で勉強しましょう。
このブログでは、あくまでパーツの用意に特化していきます。他のマネジメント領域のサンプル論文も用意していますので、ぜひご活用いただければ幸いです。



コメント